介護コラム
介護職の運動量や消費カロリーはどれくらい?
介護福祉士
ケアマネージャー
知識
介護職

身体介護では利用者の移動介助や移乗、食事・排泄介助といった直接的な力仕事や中腰・前かがみの姿勢が多く、生活援助では調理、洗濯、掃除、買い物などの日常作業が運動量に影響を与えます。本記事では、介護職における運動量と消費カロリーの実態について、業務ごとの特徴や実際の動作例を交えながら詳しく解説します。さらに、具体的な運動不足解消策や業務中の動作改善方法にも触れ、介護職として安心して働ける体作りの手助けを目指した内容となっています。
介護職の仕事内容別の運動量
介護職は利用者の身体的なサポートや日常生活の援助を行う中で、それぞれの作業内容に応じた運動量が発生します。業務内容により、歩行や立ち仕事、力仕事が求められるため、消費カロリーや体力の消耗量にも大きな違いがあります。ここでは、身体介護と生活援助という大きく分けた2つのカテゴリーについて、具体的な作業内容別に運動量の特徴を詳しく解説します。
身体介護における運動量
身体介護は利用者の身体機能を支えるために行われる作業で、直接的な身体的接触や持ち上げ、支えなどの動作を伴います。これにより、介護職員自身がかなりの運動量を消費し、筋力や持久力が求められます。
移動介助・移乗介助
移動介助や移乗介助は、利用者のベッドから車いすへ、またはトイレや浴室への移動をサポートする作業です。これらの作業では、立位や半立位の保持、そして利用者の体重を支えるための筋力が必要となり、長時間の作業や連続した移動時には身体に大きな負荷がかかります。加えて、移動介助時にはバランス感覚や適切な姿勢の維持が重要であり、消費カロリーが高くなる傾向にあります。
食事介助・排泄介助
食事介助では、利用者が安全に食事を摂取できるよう、姿勢のサポートや食器の管理、時には軽い身体介助を行います。また、排泄介助はトイレへの誘導や、場合によっては体位の補正を伴うため、短時間でも集中して筋力を使用します。、複数回にわたる介助の繰り返しにより、累積的な運動量が発生し、身体全体の疲労度は溜まります。
生活援助における運動量
生活援助は利用者の日常生活をサポートする役割を担い、家事全般や外出の付き添いなどが含まれます。身体介護ほど直接的な肉体労働ではないものの、長時間にわたる立ち仕事や微細な動作の繰り返しにより、全身の持久力が消費されます。
調理・洗濯・掃除
調理、洗濯、掃除といった家事作業は、立ったままの作業や、繰り返される体の動かし方が特徴です。厨房での食材の準備や調理器具の扱い、洗濯物の運搬、広い居室の掃除など、各作業ごとに異なる体の使い方が要求され、特に腰や足への負担が大きくなります。これにより、日常的な運動量が積み重ねられるとともに、エネルギー消費量も増加します。
買い物・外出同行
買い物や外出同行は、介護職員が利用者と一緒に外部に出かける場合に行われ、移動距離が長くなる場合があります。徒歩での移動や公共交通機関の利用、階段の上り下りなど、様々な環境下での移動作業は、歩行による運動量が大きく、また環境の変化に対応するための集中力も必要となります。これにより、屋内作業と比較して、より多くのエネルギーを消費し、心肺機能の向上にも寄与する可能性があります。
介護職の1日の消費カロリー
仕事中の消費カロリー
介護現場では、利用者への身体介護や生活援助をはじめとする様々な作業が含まれており、日中の活動中に多くのカロリーが消費されます。例えば、利用者の移乗介助や食事介助、排泄介助などは、立ち仕事や中腰の姿勢を強いられるため、短時間でも心拍数が上昇し、それに伴いエネルギー消費が増加します。また、直接的な力仕事や移動の多い作業では、筋力を使いながら体を動かすことで、約300~500kcal以上の消費が見込まれる場合もあります。
実際の消費カロリーは、各施設の業務内容や利用者の状態、そして介護職員個々の体格や体力によっても大きく変動します。複数の作業が連続する中で、一日の総消費カロリーが計算されるため、仕事中だけで1日あたり1000kcal以上を消費することも一般的です。これにより、介護職は運動量の多い職業として知られており、日々の体調管理や栄養摂取が非常に重要となります。
通勤や休憩時間の消費カロリー
介護職の消費カロリーは、勤務中だけでなく、通勤時間や休憩中の活動によっても増加します。多くの介護職員は、徒歩や公共交通機関を利用して通勤しているため、出発前や終業後の移動でも一定のカロリーが消費されます。特に徒歩通勤の場合、階段の昇降や歩行速度によっては、1日の通勤時間で100~200kcal程度の消費が期待できます。
また、昼休みや移動の合間に短い散歩やストレッチを行うことで、血行が促進され、エネルギー消費がさらに増加する効果もあります。短時間の軽い運動がリフレッシュ効果をもたらすと同時に、日常的な活動の中での消費カロリーを補完しているのです。こうした日常的な動きも、介護職としての全体のカロリーバランスに大きな影響を及ぼす要因となります。
基礎代謝による消費カロリー
全ての人間は、安静時においても体内でエネルギーが消費される基礎代謝を有しています。介護職員でも、この基礎代謝は欠かせない要素であり、自身の体温維持や臓器の働きを支えるために一定量のカロリーが毎日消費されています。一般的に、成人女性で約1200~1400kcal、成人男性では約1500~1700kcal程度の基礎代謝が見込まれますが、個人差や年齢、体重、筋肉量などによって変動します。
基礎代謝は、仕事中や通勤時間とは別に日々の消費カロリーを構成する重要な要素です。特に、介護職のように動きが多い職種では、基礎代謝と作業時の運動による消費カロリーが組み合わさることで、1日の総消費カロリーが大きくなります。そのため、介護職員は十分な栄養補給と休息を取り、エネルギーの補充をしっかり行うことが、健康維持とパフォーマンス向上に直結します。
介護職の運動量が多い理由
立ち仕事・歩き仕事が多い
介護職は、利用者のケアや日常生活のサポートのため、常に立ち上がり歩行する必要があります。施設内の各エリアを移動しながら利用者の居場所に合わせたサービスを提供するため、歩く距離が長く、連続した立ち仕事になることが多いです。これにより、心肺機能の向上や下半身の筋力強化が促され、自然な運動量の増加につながっています。
実際に、介護施設内では利用者の安全確保のため、迅速な移動が求められる場面が多く、突発的な歩行や階段の昇降など、様々な場面で運動負荷がかかります。加えて、動きの多い環境により、消費カロリーも上昇し、体全体の健康維持に寄与しています。
中腰姿勢や前かがみ姿勢が多い
介護現場では、利用者の介助の際に中腰姿勢や前かがみ姿勢をとることが頻繁に見受けられます。例えば、利用者の体位変換や起き上がりのサポート、見守りのための低い位置からのコミュニケーションなど、無理のない姿勢でケアを行うために、自然と体を曲げる動作が多くなります。
こうした姿勢は、腹部や背中、下半身の筋肉を効果的に使い、持続的な筋力トレーニングと同様の効果をもたらします。さらに、正しい姿勢の維持や負担を軽減するために、日々の体力トレーニングの必要性を感じさせる要因ともなり、結果として介護職全体の運動量が増加する背景となっています。
力仕事が多い
介護現場では、利用者の移乗介助や体位変換、車椅子の操作など、力を要する作業が多く発生します。これらの作業は、背中や腕、脚の筋力を大いに活用するため、一回あたりの運動負荷は比較的高くなります。利用者の体重や移動のタイミングに応じた力加減が求められるため、無理のない介護を行うためにも適切な体力が必要となります。
また、日常的に重い介護用具や移乗補助具を使用する現場では、力仕事が多いことから、全身の筋肉バランスの維持や柔軟性向上を目的としたトレーニングが欠かせません。このような業務内容が積み重なることで、一日を通してかなりの消費カロリーとなり、自然と運動量が増加する結果となっています。
介護職に必要な体力と体力維持の方法
介護現場では、利用者に対する身体介護や生活援助などの業務を安全かつ適切に行うために、十分な体力が求められます。本節では、介護職に必要な体力の種類と、その体力を維持・向上させるための運動方法について詳しく解説します。
必要な体力の種類
介護職では、長時間の立ち仕事や歩行、持ち上げる動作など、日常的に多岐にわたる身体的負担がかかります。そのため、まずは全身の筋力が重要です。特に、腕、背中、脚の筋力は、介助作業に不可欠です。また、持久力も重要で、長時間勤務中の疲労軽減や、業務に必要な集中力を維持するためには、心肺機能の向上が求められます。さらに、柔軟性やバランス感覚も、急な体勢変換や不安定な状況下での転倒防止に役立ちます。
効果的な運動方法
介護職に必要な体力を維持・向上するためには、計画的な運動習慣が大切です。ここでは、筋力向上と有酸素運動という二つの観点から効果的な運動方法をご紹介します。
筋力トレーニング
筋力トレーニングは、介護作業に必要なパワーと耐久性を養うために非常に有効です。例えば、自宅やジムでのダンベルやケトルベルを用いたトレーニングは、上半身および下半身の筋力をバランス良く鍛えることができます。また、スクワットやプランク、腕立て伏せといった自重トレーニングも、器具を使わずに行えるため、日常生活に取り入れやすい運動方法です。これらの運動は、正しいフォームを維持しながら無理のない範囲で段階的に負荷を増やしていくことが望まれます。
有酸素運動
有酸素運動は、心肺機能の向上と持久力を増強するために効果的です。ウォーキングやジョギング、サイクリングなどは、比較的負担が少なく、継続しやすい運動として推奨されます。特に、介護施設への通勤や業務終了後に、近隣の公園を利用したウォーキングは、心身のリフレッシュ効果も期待できるためおすすめです。また、エアロビクスなどのグループレッスンに参加することで、運動習慣の形成とともに、同僚や地域の仲間との交流も深めることができます。
日常生活でできる運動
忙しい介護職の現場でも、隙間時間を利用して取り入れやすい運動は、普段の生活の中での工夫次第で十分な効果が得られます。例えば、エレベーターではなく階段を使う、通勤時に一駅分歩く、休憩時間にストレッチや軽い体操を行うなど、日常の動作に運動の要素を取り入れることで、筋力や柔軟性の向上が期待できます。
また、家庭でも、テレビを見ながらラジオ体操やヨガを実施することは、手軽に体力維持に寄与します。さらに、週末には自転車で近所を散策するなど、楽しみながら体を動かす習慣を作ることが、長期的な健康維持につながります。
介護職の運動不足解消のための工夫
勤務中の工夫
介護施設や病院などの現場では、業務中の合間にも軽い運動を取り入れることが大切です。例えば、利用者様のケアを行う際に、立ち上がりや体重移動を意識して行うことで、筋力やバランス能力を高める効果が期待できます。また、移動介助や物品の整理整頓の際に、意識的に深呼吸やストレッチを取り入れることで、体が硬直するのを防ぎ、血流を促進することができます。
勤務中に短い休憩時間を設け、休み時間にその場でできる簡単なストレッチやウォーキングを行う工夫も重要です。施設内で使えるスペースが限られている場合は、廊下を歩いたり、事務所内で軽いエクササイズをすることで、日常の業務の中で少しずつ運動量を増やすことができます。加えて、同僚同士で合間の運動を促す声掛けや、運動のタイミングを決める工夫が、モチベーション向上にもつながります。
休憩時間の活用
休憩時間は、心身のリフレッシュとともに適度な運動を取り入れる好機です。施設内にストレッチスペースや簡易の運動機器がある場合は、それらを活用して短時間でも身体を動かすことが推奨されます。実際に、チェアヨガや軽いストレッチは、腰痛や肩こりの予防に効果的です。
また、屋外に出られる環境であれば、休憩時間中に短い散歩を取り入れると、自然光を浴びながらリラックス効果とともに有酸素運動の効果も得られます。平日の昼休みや勤務後の少しの時間を利用して、施設周辺を歩く習慣を持つことで、心身のリフレッシュにつながるだけでなく、運動不足の解消にも大いに寄与します。
休日の過ごし方
休日は、平日の業務で蓄積した疲労を癒すとともに、計画的に運動を取り入れることが重要です。朝の散歩やジョギング、または地域のジムやフィットネスクラブでの筋力トレーニングなど、定期的な運動習慣を取り入れるとよいでしょう。特に、ウォーキングやサイクリングは、負担が少なく続けやすい有酸素運動として多くの介護職の方に推奨されています。
また、週末に参加できる地域のフィットネスイベントや介護職向けの健康セミナーなどに参加するのも、モチベーションアップにつながります。さらに、家族や友人と一緒にスポーツを楽しむことは、ストレス発散とコミュニケーションの向上にも効果的です。休日の過ごし方を工夫することで、仕事とプライベート双方での健康管理が実現できます。
運動量の管理方法と注意点
介護現場では、身体にかかる負荷が大きいため、日々の運動量の管理がとても重要です。適切な管理を行うことで、無理のない作業が可能になり、長期的な健康維持やケガの予防につながります。この章では、運動量の把握方法、疲労のサインへの対処法、そして水分補給の重要性について詳しく解説します。
適切な運動量の把握
介護職では、立ち仕事や多くの歩行、介助動作などにより多量のカロリーが消費されます。自分の運動量を正確に把握するためには、活動量計やスマートウォッチ(Apple Watch、Fitbitなど)の活用が有効です。これらのデバイスは、歩数や心拍数、消費カロリーをリアルタイムでモニタリングできるため、日々の運動負荷を数値として記録することができます。
さらに、健康管理アプリケーションを利用することで、記録したデータを基に自分の運動パターンや体力の変化を把握することができます。定期的に見返し、日々の業務に合わせた無理のない運動プランを立てることが、健康維持や業務効率の向上につながります。
疲労のサインを見逃さない
長時間の立ち仕事や介助作業により、身体には必ずしも同じペースで疲労が蓄積されないわけではありません。肩こり、腰痛、足のむくみや筋肉の張りなどは、体からのサインです。こうした初期のサインを見逃さずに、適切な休息を取ることが重要です。
もし、疲労を感じた場合は、作業の合間に軽いストレッチを行う、深呼吸をするなどして、体のリフレッシュを心がけましょう。症状が長引く場合は、上司や同僚と相談しながら、作業の割り振りを見直したり、専門の医療機関で診てもらうことも大切です。日々の体調管理は、介護職で働く上での基本となります。
水分補給の重要性
介護職は、長時間立ちっぱなしの作業や肉体労働が多いため、体内の水分が失われやすい環境にあります。十分な水分補給がなされないと、脱水症状や熱中症のリスクが高まります。作業中は忙しさにかまけて水分摂取を忘れがちですが、定期的に水分を補給することが健康維持のために必要です。
業務の合間に、常温の水やミネラルウォーター、スポーツドリンクなどを適量摂ることを習慣化しましょう。また、夏場の高温多湿な環境や、エアコンが効きすぎた冬場でも水分補給は欠かせません。自分の汗の量や体調に応じ、こまめな水分摂取を心がけることで、集中力の維持や体調管理がスムーズに行えます。
まとめ
本記事では、介護職の運動量や消費カロリーの実態を、身体介護と生活援助それぞれの仕事内容に基づいて詳しく解説しました。立ち仕事や歩行、中腰姿勢、力仕事といった特有の動作が、日々のエネルギー消費に大きく影響するため、正確な運動量の把握と適切な体力管理が重要です。勤務中、休憩時、休日における積極的な運動やリフレッシュの工夫が、健康維持と安全な介護現場の実現につながります。
メディケアキャリアで
北信越の介護職求人を探す
関連記事
-
20代で介護職に転職するには?転職を成功させるコツを紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職

更新日:2025年03月18日
本記事では、20代で介護職への転職を考えている方に向け、転職活動が成功するための具体的なコツやポイントを網羅的に解説します。
詳しく読む
-
介護士が行うエンゼルケアとは?流れや手順などを紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職

更新日:2025年03月18日
本記事では、介護士が実践するエンゼルケアの定義や目的、そしてターミナルケアとの違いについてわかりやすく解説します。
詳しく読む
-
介護士はお盆休みや連休が取れない?取得しづらい理由や対処法を紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職

更新日:2025年03月18日
本記事では、介護士が抱えるお盆休みや連休の取得の現状と、その背景にある業務の性質や人手不足、利用者家族の事情など複数の要因について詳しく解説します。
詳しく読む
-
介護職で腰痛になったら労災認定される?条件や申請の流れなどを解説
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職

更新日:2025年03月18日
本記事では、介護職における腰痛がどのような条件で労災対象となるのか、業務起因性や業務遂行性の具体的な基準、さらには必要な書類や申請手続き、給付内容などを解説します。
詳しく読む
-

更新日:2025年03月18日
20代で介護職に転職するには?転職を成功させるコツを紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職
本記事では、20代で介護職への転職を考えている方に向け、転職活動が成功するための具体的なコツやポイントを網羅的に解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年03月18日
介護士が行うエンゼルケアとは?流れや手順などを紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
知識
介護職
本記事では、介護士が実践するエンゼルケアの定義や目的、そしてターミナルケアとの違いについてわかりやすく解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年03月18日
介護士はお盆休みや連休が取れない?取得しづらい理由や対処法を紹介
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職
本記事では、介護士が抱えるお盆休みや連休の取得の現状と、その背景にある業務の性質や人手不足、利用者家族の事情など複数の要因について詳しく解説します。
詳しく読む -

更新日:2025年03月18日
介護職で腰痛になったら労災認定される?条件や申請の流れなどを解説
全職種
介護福祉士
ケアマネージャー
訪問看護
看護助手
介護事務
知識
介護職
本記事では、介護職における腰痛がどのような条件で労災対象となるのか、業務起因性や業務遂行性の具体的な基準、さらには必要な書類や申請手続き、給付内容などを解説します。
詳しく読む
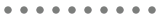

 0800-222-6155
0800-222-6155

 0800-222-6155
0800-222-6155


